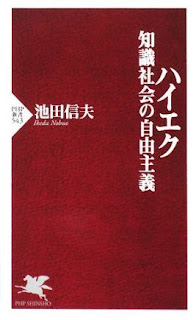ここのところ世界的に再評価の動きが高まっている経済学者
フリードリヒ・フォン・ハイエクの仕事を要領よくまとめた本。ハイエクという人物を題材にした20世紀の経済学史という趣で、非常に面白い。
社会主義計算論争
ハイエクの経済思想を理解するためには、「社会主義計算論争」(p.53)という史上もっとも有名な経済学論争をたどるのがおそらく最もよい。この論争は、オーストリアの経済学者
フォン・ミーゼスが、社会主義経済には所有権も価格もないので効率的に財を分配することはできないと指摘したことに端を発する。1920年代のことである。
これに対して
オスカー・ランゲら社会主義派の経済学者は、仮に明示的に価格や所有権がなくても、「中央計画委員会(Central Planning Board)」が、生産をつかさどる各部門から需給についての情報を集め、財についての全体がバランスするようにやり取りを調整すれば、完全な市場と同様の機能を果たせると主張した。1940年代にはそれが具体的に線形計画法という最適化問題として扱えることが示され(p.56)、さらにその後、その解が、新古典派の均衡解と一致することが示された。すなわち、社会全体を巨大な
線形計画問題として定式化することができ、最適な財の配分のためにはそれを解きさえすればよいということが、少なくとも理論的には示されたのである。ある意味で社会主義的計画経済の最適性が示されたということである。
ミーゼス陣営に加わったハイエクは、市場メカニズムについての深い思索に基づいて、主に「知識の分業」の観点から社会主義的計画経済の不合理性を指摘した。ハイエクは問いかける。
If we possess all the relevant information, if we can start out from a given system of preferences and if we command complete knowledge of available means, the problem which remains is purely one of logic. (F. A. Hayek, "The use of knowledge in society," The American Economic Review, Vol. 35, Issue 4, pp.519-530 (1945).)
すなわちハイエクとっては、中央計画委員会が経済事象についての必要十分な知識を持っているという前提自体が受け入れがたいものであった。その前提を受け入れてしまえば、上記のように問題は数学的に解けてしまうのだが、ハイエクは、計画経済の最大の問題が、いかにして分散した知識を集約するかという点にあると考えた。そしてハイエクは、それが事実上不可能であることを指摘したのである。
市場取引の動機となる知識は、誰もがアクセスできる自然科学上の法則のようなものではなく、個々人のまわりの個々の環境に依存している。そして個々のプレイヤーの嗜好も様々である。そしてそれらは時間と共に大きく変化する。市場システムは、そのような異種混合的な社会の、局在した知識をコーディネートする仕組みとして機能している。ハイエクは言う。
If we can agree that the economic problem of society is mainly one of rapid adaptation to changes in the particular circumstances of time and place, it would seem to follow that the ultimate decisions must be left to the people who are familiar with these circumstances, who know directly of the relevant changes and of the resources immediately available to meet them. (F. A. Hayek, ibid.)
すなわち、そのようなコーディネーションは、中央計画委員会が何か能動的に行うようなものではなく、それぞれのプレイヤーの自由な選択の結果として現れてくるものだとハイエクは考えたのである。
しかしこのような考え方は多くの経済学者の受け入れるところにはならなかった。1930年前後の世界では、大恐慌は資本主義のシステム的欠陥を明示しているように思われたし、一方で、史上初の社会主義革命がロシアで起こり、社会主義経済の政治的実装が現実のものになっていた。特に知識階級においては、社会主義はこの世から不幸を一掃する福音のように受け止められていたはずである。
この時代状況において、いわば消極的な不可知論を繰り返すハイエクらの思想がどういう評価を得たかは想像に難くない。この論争に敗れた(とコミュニティから受け止められた)後、ハイエクは長い間、頑迷な保守反動の象徴として経済学研究の表舞台から消えることになる。
ハンガリーでの実験
しかし話はこれで終わりではなかった。1960年代になり、社会主義国ハンガリーの経済学者コルナイは、実際にこの理論を実行に移した。すなわち生産の各部門から上げられたデータを基に線形計画法を解いて、実際に計画経済を実行した。
その結果は、21世紀を生きる我々にはもはや説明するまでもなく、惨憺たる失敗に終わった。本書にはコルナイ自身の回顧録が引用されている。
この問題を今の頭で考え直して見ると、ハイエクの議論にたどりつく。全ての知識、全ての情報を、単一のセンター、あるいはセンターとそれを支えるサブ・センターに集めることは不可能だ。知識は分権化される必要がある。情報を所有する者が自分のために利用することで、情報の効率的な完全利用が実現する。したがって、分権化された情報には、営業の自由と私的所有が付随していなければならない。(p.59)
結局この論争は、ハイエクらのいわば逆転勝利に終わったわけである。しかもその後西側先進国はいわゆる
スタグフレーションを経験し、ハイエクらを駆逐したはずの新古典派経済学の無力ぶりに不満が高まった。そしてつい最近の
サブプライムローン問題は、最新の金融工学の適用限界を明らかにした。今、ハイエクの経済学的主張に通底する哲学に注目が集まるのはそういう理由である。
本書にはこの社会主義計算論争をめぐるエピソードをはじめ、ケインズとの関係、New classical 派の紹介など、経済学上の非常に多彩な話題に満ちている。その他、話題は最新の実験経済学の成果や、人工知能の歴史にもおよび、著者
池田信夫氏の恐るべき博識を示して余りある。私は本書を、現代のインテリゲンチャ必読の書だと思う。
多体問題の困難
しかしひとつ注意しておきたいのは、自然科学、とりわけ現代物理学についての著者の理解は浅く(それでも博識であるが)、私のような者の目から見ても違和感のある表現が散見されるということだ。
本書の記述に細かい注釈を付けるのはまたの機会に譲り、ここでは現代物理学の常識を示す話題を2つだけ提供しよう。ひとつが
多体問題であり、もうひとつがAndersonの"more is different"である。
社会主義計算論争におけるハイエクの主張は、「知識の集約不可能性」という概念にまとめられる。実はこれは物理学上はありふれた概念である。たとえば、すでに18世紀において、多体系の解を求めるのが絶望的に難しいことはよく知られていた。やや驚くべきことだが、運動方程式の一般解が求められるのは2体問題までで、3体問題以上は、特殊な条件の下でしか解くことはできない。
ラクランジュの正三角形解、
コワレフスカヤのコマ、などがその特殊な例である。すなわち、個々の相互作用(天体の場合は重力)が既知であったとしても、それを集約して全系の動きを一望することは特別な場合を除いてできない。それができるのは、相互作用がないときである。
これに対して天文学者たちは摂動法という手法を編み出した。これは相互作用が小さいという仮定の下に、級数展開のようにして、多体効果を順次取り込んでゆく手法である。天体力学の場合、ほとんどの現象はこれでカバーできるが、20世紀、量子力学の時代になると、「相互作用が小さい」という仮定がまったく成り立たない現象が非常に多く見出され、人類は多体問題の本質的難しさに再び直面することになった。「凝縮系物理(condensed-matter physics)」とか「物性物理(solid-state physics)」とか、あるいはもっと直裁に「強相関系の物理(physics of strongly-correlated systems)」とかいうのは、そういう状況を強調するために使われる言葉である。今の文脈に即して言えば、電子同士の相互作用がクーロン相互作用という形で既知であったとしても、集団としての電子の振る舞いを正確に記述するのは絶望的に難しい。そこでは、個々の集積から想像されるのとはまったく別の、非常に多彩な現象が実現される。
いわばこれは秩序の自律的形成とも言える。著者は人工知能研究におけるコネクショニズムを指して、「ハイエクが、この理論をコンピューターも脳科学もなかった時代に、ほとんど『深い思考』だけで創造したのは驚くべきことである」と述べているが(p.83)少なくとも物理学的にはありふれたモチーフである。
凝縮系物理の研究を、
新しい古典(New Classical)派の理論に対比させて みるのは興味深い。新しい古典派の経済学では、いわば、均衡理論というマクロ理論から、それを実現するようなミクロなダイナミクスが導かれる格好になっている(逆も真である)。その結果導かれる個々のプレイヤーの振る舞いは、通常、我々が想定する個人とは大きく乖離する。それが「非現実的」だとの批判がこれまで頻繁になされ、埋めがたい方法論的対立が存在するようである。新しい古典派にとっては、「仮説が現実的かどうかはどうでもよい。重要なのは、その仮説から導かれる結論が実証データに合うかどうかだ」(p.116)。
このあたりの議論は、経済学のセクショナリズム的傾向を示して興味深い。物理学でも同様のことはよくある。たとえば「
重い電子系」という用語がある。電子の質量は基本的な物理定数のひとつで、それが重くなったり軽くなったりということはありえない。電子が重い、ということの主旨は、「もし電子の質量を可変なパラメターだと想像してみると、あたかも質量が重い電子があるように見える」ということに過ぎない。物理学ではそのように可変な変数のように扱われる質量を「
effective mass」などと呼ぶ。effectiveというのは、「真実はそうでないかもしれないが、実効値としてはそういうもの」という語感である。
この用語を使えば、新しい古典派の人間像は、いわば effective personないしeffective interactionからなるものである。それは間違いなく現実の人間の振る舞いとは異なるが、現実を説明する限りにおいて、理論モデルとして是認されるのである。しかしあくまでそれは現象論(現象の真のメカニズムの解析を省略して現象を記述しようとする理論)に過ぎず、その有効範囲は限定的である。物理学では「現象論」という言葉はしばしば軽蔑的に使われるが、有効範囲が限定的であることを忘れなければ、工学的にはむしろより重要な武器となる。その価値は現実をどのようによく説明するかで判断されるのであり、有効質量を導入したこと自体で神学論争のようなことが起こることは少ない。
More is different
20世紀初頭の量子力学誕生は、古典力学の唯一絶対性を否定したが、量子力学が登場したからといって、古典力学が無効になったわけではない。同様に、当初の量子力学は、たとえば相対論的量子力学の近似理論に過ぎないが、だからといって、シュレーディンガー方程式は無効ということにはならない。自然現象には異なる階層があり、それぞれの階層において最適な方法論がある。おそらく経済現象もそうであろう。経済学の困った点は、異なる学派同士の関係がはっきりせず、それぞれの有効範囲も不明であるという点である。
この点を考える上では、1977年にノーベル物理学賞を受賞した大御所
P. W. Anderson の1972年のエッセイが示唆的である*。この短いエッセイでAndersonは、自然現象には階層性があり、素朴な要素還元主義は実り多い視点ではないと指摘した。more is different というタイトルの通り、下位の構成要素が多数集まると、個々の要素を見ているだけでは思いもかけない多彩な現象が現れる。だから、上位の階層は下位の階層に還元することはできず、階層に応じた別の方法論が必要である。これは物理学者には改めて言うまでもない当たり前のことだが、物性物理よりも、物質の究極の粒子を追い求める理論の方が高尚だ、というような一部の風潮にひと言言いたかったのであろう。
* P. W. Anderson, "More Is Different," Science, Vol. 177. No. 4047, pp. 393 - 396 [link to pdf]
若きハイエクがテーマとした知識の分業についても、おそらくこのような視点が必要であろう。経済学の分野では、ハイエクの自律分散の思想には、最近でもなおたとえば次のような批判が浴びせられる。
Yet this is surely an abusurd thesis. First, if the centralized use of knowledge is the problem, then it is difficult to explain why there are families, clubs, and firms, or why they do not face the very same problems as socialism. Families and firms also involve central planning. (Hans-Hermann Hoppe, "Socialism: A Property or Knowledge Problem?," The Review of Austrian Economics, Vol. 9, No. 1, pp.143-49, 1996.)
この批判は、家族や会社組織と、社会全体との間の現象の粒度の違いをまったく考慮に入れていない。そもそも民主主義ですらない家庭や会社組織の中では中央管理が自然で必然であるが、社会の粒度ではそうではない。それがMore is differentということである。しかしこの概念を経済学者たちが理解するには、まだ時間がかかりそうである。サミュエルソンは古典力学をモデルにして彼の新古典派総合の理論を作ったそうだから、理論的モチーフにおいてはまだ2世紀ほどギャップがあるのかもしれない。
ハイエク ── 知識社会の自由主義 (PHP新書)
- 池田 信夫 (著)
- 新書: 224ページ
- 出版社: PHP研究所 (2008/8/19)
- ISBN-10: 456969991X
- ISBN-13: 978-4569699912
- 発売日: 2008/8/19
- 商品の寸法: 17.2 x 10.6 x 1.4 cm